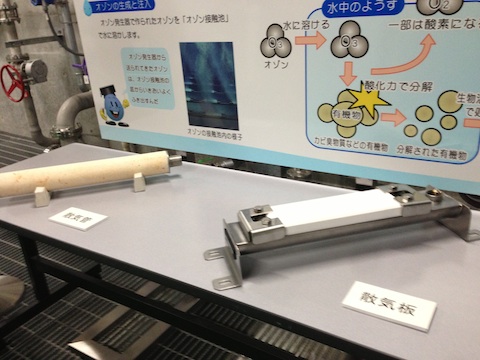4月27日に理科大葛飾キャンパスでイベントがあったので見に行きました。大学内の図書館などが一般公開され、大学生のサークル活動の発表会なんかがあったみたいです。ピーター・フランクルさんがトークショーもしたらしいんですが、あまり時間がないのでそれは見ませんでした。
▲金町のイトーヨーカドーの前の道です。この日は理科大葛飾キャンパスでイベントがあるというので賑やかでした。
▲この立派な建物は理科大の図書館棟です。これだけ見てるとここが金町とは思えない景色です。
この日は大学の図書館も一般公開されてました。入ってみたところ、電源付きのテーブルが沢山あり、ノートパソコンでメモをとりながら本を読むのによさそうです。羨ましいぞ大学生!
なお、ここの本は葛飾区立図書館の利用カードを持っていれば5月7日から理科大生でなくても借りられるそうです。ただ、この日見た感じだと蔵書がかなり偏ってました。大学の教材ですから仕方ないですね。
今後もっと蔵書が増えるでしょうし、生物系の資料が充実するといいなあ、なんて個人的には思ってます。
▲これは図書館棟にある未来わくわく館です。子供も大人も楽しめる科学体験ができる施設です。入場は無料。9〜17時、土日もやってます。休館日は第三月曜日とのこと。
この日はイベント中でこのとおり賑やかでしたけど、平日はだーーーれも居ませんからシャイな大人はずる休みして平日にどうぞ(笑)
わたしも平日に改めて遊びに行きました。アルキメディアンスクリューで水を高いところに運ぶ実験や、ドライアイスの雲で竜巻や台風を作る実験、白黒なのに回すと虹色に見えるベンハムのコマを体験できるコーナーなど、けっこう楽しいです。
でも一番人気は風速12m/sを体験できる部屋でしょうか。わたしのあとに来た人たちもこの部屋に入ってキャーキャー大喜びしてました。最高速の12m/sに達すると、まっすぐ立ってられない感じになりますよ。
# ただ、それほど規模は大きくないので、このまま展示が固定だとわりとすぐ飽きられそうな悪寒もします。せっかくの施設ですし、定期的に入れ替えてリピーターを増やしちゃったりするんですよね? と、どこか遠くのお空にむかってつぶやいてみるテスト。
▲この錆びた丸い物体は通称「むしがま君」といって、紙を蒸してリサイクルするための釜だそうです。理科大葛飾キャンパスは三菱製紙中川工場の跡地に作られました。製紙工場は数年前に移転して当時の名残はほとんどなく、この釜だけが記念碑として残されました。
▲近付いてみました。芝生の養生中でこれ以上は近づけませんでした。夏になったらもうちょっと近くまで行けるかもしれません。
大学内には生協や学食やカフェもあり、どうやら一般利用OKのようです。生協は小さくてコンビニとあんまりかわりません。学食は大手ファミレスとコラボでやけにおしゃれなものが食べられるようです。カフェには葛飾(かつ"シカ")にちなんで鹿肉のハンバーガーなんかもあるみたいですよ。
というわけで、区民の憩いの場にもなりそうな素敵なキャンパスができました。場所は、金町駅(JR・京成)から徒歩10分くらいです。
大きな地図で見る
タグ:地元(葛飾周辺)