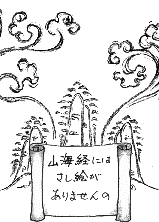 |
シュエン
獣がいる。そのかたちは猿のようで白い首と赤い足を持ち、名は朱厭という。これが現れると大戦がおこる。(西山経二の巻)--071 ヨウワ
文は『山海経』より |
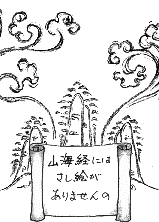 |
シュエン
獣がいる。そのかたちは猿のようで白い首と赤い足を持ち、名は朱厭という。これが現れると大戦がおこる。(西山経二の巻)--071 ヨウワ
文は『山海経』より |
| 朱厭や雍和のモデルになったのはどんなサルだろう。郭璞はこの件に関してなにも注釈を残していないし、手がかりは少ない。
朱厭については「猿のようで」とある。『山海経』ではサルを意味する漢字に「禺」を使うことがほとんどだが、ここではあえて「猿」となっているところに注目しよう。 中国にはサルを意味する漢字が沢山ある。そのひとつひとつに明確な意味があるとは言い切れないが、おおざっぱな使い分けはあるようだ。 「猿」という字は「けものへん+爰」と書くのが本来の形だという。爰は引く動作をあらわすので、木をひっぱる獣、つまりテナガザルを意味する文字だという。長い腕で木をつかみ、体を振った反動で次の枝をつかみ、これを繰り返して木から木へと渡ってゆくタイプのサルのことだ。 テナガザルと呼ばれるものには何種類かいて、毛が白や灰色になるものも多い。ただし、どれも顔や手のひらが黒く、朱厭のように白い首(頭)と赤い足というのはいない。 もっとも、現れると大きな戦が起こるというのだから、そういった当たり前の生き物ではなく、突然変異のような特殊な状態のサルなのかもしれない。
もし、ハヌマーンと関係があるのなら、名前からそのままのハヌマーンラングールなど候補にあがりそうだ。『ラーマーヤナ』の猿王ハヌマーンはこの猿がモデルと言われていて、インドの寺院では大事にされている。 しかし、ハヌマーンラングールは顔や手足が黒く、朱厭や雍和と体色が違う。 |
 ハヌマーンラングール ハヌマーンラングール
「ラングール」とは、サンスクリット(インドの古語)でやせた猿という意味。 |
テナガザルだのオナガザルだのいう分類は最近になってなされたものだし、単純に手足の長いサルを猿と言ったかもしれない。たとえばラングールと呼ばれるサルなども、古代中国人が見れば「猿のようで」となりそうだ。 左の図のハヌマーンラングールはインドの猿で顔や手足が真っ黒だが、東南アジアに住むドゥクラングールは顔が白っぽい。 |
| 朱厭は、それが現れると大きな戦が起こるという不思議な生き物だが、同じような特徴を持つ雍和についてもふれておこう。
「サルのようで」と片仮名で表記した部分は[虫爰]となっているが、虫をけものへんにかえれば猿と同じ字になる。
つまり、雍和も朱厭と同じく手長系のサルだということだ。 ※ 文中の[ ]内は一文字として読んでほしい。 |
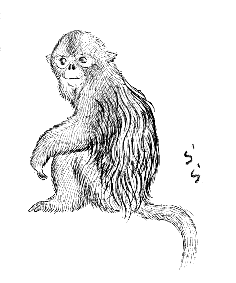 キンシコウ(ゴールデンモンキー) キンシコウ(ゴールデンモンキー)
古来その美しい毛皮が喜ばれ、骨などは漢方薬として珍重された。また開発が進んだせいで住処を失い、現在は絶滅の危機に瀕している。 |
|
雍和は黄色の毛を持つとあるので、キンシコウというサルが当てはまるかもしれない。つやのあるオレンジ色の毛を持つサルで、孫悟空のモデルになったとも言われている。もっとも、キンシコウの顔はどちらかと言うと青っぽい。それに、キンシコウは猿と呼ばれるサルのように手足は長くない。どちらかといえば「猴」という字であらわしたほうが良さそうなサルである。 もっとも『山海経』には猴という文字がひとつも出てこない。この時代には猴という文字がなかったか、あるいは明確に使い分けてはいなかったのかもしれない。 |
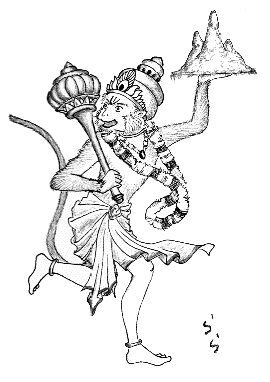 ハヌマーン ハヌマーン
インド神話にでてくるスーパーモンキー。 |
ところで、雍和と朱厭はどちらも戦いや騒ぎの前触れとされている。
サルと大騒ぎで連想するのは『西遊記』の孫悟空であろう。岩から生まれた妖力を持ったサルが、三蔵法師の家来になって天竺に教典を取りにゆくという物語だ。 西遊記そのものは作者のいる空想小説だが、完全な創作ではなく、それ以前に伝説化していた物語をまとめたものだとも言われる。もしかしたら、孫悟空のような暴れサルの伝説が『山海経』の頃にすでにあったのだろうか? またインドには『ラーマーヤナ』という壮大な叙事詩がある。ラーヴァナと呼ばれる魔神を退治するために、ヴィシュヌをはじめとする神々が地上に転生して戦いを挑むという話だが、
|
| ☆まめちしき
『山海経』の雍和の説明文の中に、「喙(くちさき)」という文字が出てくるが、簡単に言えば「くちばし」のことだ。日本語で「くちばし」というと、鳥のものを想像しがちだが、「喙」は獣の口の意味も含んでいる。獣の口はたいてい鼻面になって突き出しているし、鳥のくちばしもとがっていて、共通のイメージなのだろう。 まったく蛇足になってしまうが、アイヌ語では鼻のことをエトゥという。鳥のくちばしのこともエトゥである。どっちも顔の真ん中で一番とがっているところだからだ。 |
|
|